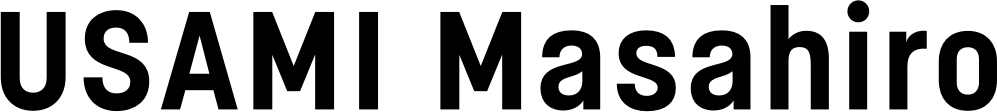会期:5月16日(木)- 5月25日(土)
時間:水〜土 : 12:00-19:00 / 日 : 12:00-17:00(休廊日: 月曜・火曜)※ 5月18日(土)のみ16時まで
会場:kanzan gallery(東京都千代田区東神田1-3-4 KTビル2F / 03-6240-9807)
●オープニングパーティー
5月16日(木) 18時から20時まで
●トークイベント テーマ 「神宮外苑再開発問題とアート」
5月19日(日) 17:00 – 18:30
登壇者:望月衣塑子(ジャーナリスト)×宇佐美雅浩
予約はこちらから
https://manda-la-talk240519.peatix.com/view
定員40名程度
●宇佐美雅浩トークショー テーマ「Manda-la project」
5月25日(土)14:00-15:00
当日の先着順。念の為、定員30名程度
.
「ワークインプログレス」としての写真
近藤亮介(美術批評家、キュレーター)
昨年、東京都は公園制度150周年を盛大に祝った。その一方で、創建100年を迎えた明治神宮のランドスケープを台無しにしようとしている。大いに矛盾している。明治神宮内外苑の建設は、官民がひとつになった国家事業というだけでなく、日本の造園学誕生を象徴するプロジェクトとしても重要である。内苑の神聖な杜から外苑のイチョウ並木まで、そのランドスケープは当時第一線で活躍する園芸学、林学、建築学の専門家たちが総力を結集して取り組んだ成果にほかならない。
こう書けば、明治神宮外苑の再開発に対する私の態度は明らかだろう。しかし、このテキストの目的は再開発の是非を論じることではない。宇佐美雅浩のライフワークとも言うべき「Manda-la」シリーズの意義を問うことである。なるほど宇佐美は再開発のプロセスに疑問を呈しつつも、決して「反対」とは言わず、できるだけ中立でいようとする。本心は分からないが、これまでの作品を通観する限り、少なくとも彼はどんな立場の人にも等しく真摯に向き合ってきたと言える。
製鉄会社に勤めた亡き父、地元高校の音楽教諭、秋葉原の同人誌ショップ経営者といった家族・友人から、広島の被爆者、福島の被災者、北海道のアイヌ民族運動家といった政治性を帯びた人物まで、宇佐美は各地でさまざまな社会背景を持つ人々と徹底的に向き合い、彼らの内なる世界を1枚の写真で見事に「視覚化=曼荼羅化」してきた。特に作品が輝くのは、宇佐美が個人を超えて群集へ目を向けたときである。
例えば、キプロスでは対立が続くギリシャ正教徒とイスラム教徒が向き合い、佐渡島では多種多様な伝統芸能に従事する人々が宝船に乗って参集した。両作品のテーマはまったく異なるが、普段は同じ場所に居合わせることのない人々がひとつの願いの下に団結している点で共通する。それは、キプロスでは平和共存であり、佐渡では文化伝承である。もちろん、そのときも宇佐美は被写体ひとりひとりと丁寧に向き合い、話し合っているに違いないが、群集そのものを主人公にした写真は、より強く社会に訴えかけてくる。なぜなら、彼らの願いは作品を観る私たちにも共通する普遍的なものだからである。
新作《声なきラガーマン 神宮外苑 2023》も、主人公は特定の個人ではなく群集だ。しかし、今回の群衆はひとつの願いの下に集まってはいない。というのも、そこでは外苑再開発に対する反対派と賛成派が対峙しているからだ。画面左側では市民がスクラムを組み、スポーツに興じる一方、右側では事業者・役人(宇佐美は「システム側」と呼ぶ)がスクラムを組んだり、ノコギリを持って俯いたりしている。たしかに反対派には願いを見て取ることもできるが、本作が全体として表象するのは、むしろ分断である。
ただ、この分断は見せかけに過ぎない。それは単に写真作品だからということではなく、被写体全員が「本物=当事者」ではないからだ。これまで宇佐美は必ず当事者を集め、できるだけエキストラに頼らずに撮影を行なってきた。どんなに入念に構成された記号的で非現実的な世界であっても、当事者の真正性が画面にエネルギーを漲らせる。彼らの鋭く切実なまなざしが、鑑賞者に畏怖の念を抱かせる。しかし、本作ではそのバランスが崩れている。画面の中の彼らとは目が合わない。事業者・役人側に当事者は含まれず、全員がエキストラである。市民側はほとんどが都民だが、どのくらい当事者意識を持っているか知る由もない。さらに言うなら、現実の「システム側」には、市民として葛藤を抱えながら、組織の言いなりになっている人たちもいるはずだ。こうした当事者の不在や意識差が画面のエネルギーを減じ、「Manda-la」シリーズの中でもひときわ虚構性をあらわにしているように思われる。しかし、その薄さが、かえって再開発の根本的問題、すなわち権力者の狡猾さと市民の無関心を浮かび上がらせる。ここにも作家の真摯さが垣間見える。
実際、本作において宇佐美は撮影後も交渉を続けている。展示やトークだけでなく、マスメディアやSNSも駆使して、各方面へ働きかけている。今後、事業者・役人側の関係者に取材する機会があるかもしれない。彼は、これまでも人々との粘り強い話し合いを通じて、対立や分断を超えた人類の願いを画面に焼き付けてきた。まさしく仲介者(メディエーター)であり、交渉人(ネゴシエーター)である。つまり、宇佐美にとって写真は完成形ではなく、常に「ワークインプログレス」である。本作において宇佐美の本領が発揮されるのはこれからだ。
【近藤亮介 プロフィール】
美術批評家、キュレーター。1982 年大阪市生まれ。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン美術学部(Slade School of Fine Art)卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。ハーバード大学デザイン大学院(Graduate School of Design)フルブライト客員研究員、東京大学教養学部助教を経て、現在、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科非常勤講師。専門は美学芸術学・ランドスケープ史。日英米の芸術・造園の研究を軸に、理論と実践の両面からランドスケープを生活環境として読み解く活動を展開している。編著に『セントラルパークから東京の公園を見てみよう』(東京都公園協会、2023年)、企画・キュレーションに「アーバン山水」(kudan house 、2023 年)など。